このページでは、普通ボイラー溶接士の学科試験を最新の出題傾向から徹底的に再現した実践的な模擬問題(全40問)です。
スマホでもサクッと答えられる5択形式で、自動採点つき。採点ボタンを押すと、各問題の下に正解と詳しい解説が表示される親切仕様!是非挑戦してね。
スポンサーリンク
【過去問分析・予想】普通ボイラー溶接士 学科試験対策 模擬問題40問
—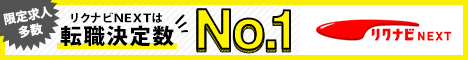
相原から一言
模擬試験、おつかれさまでした!
ここまで解ききった人、本当に立派です。
点数が思ったより伸びなくても大丈夫。
大切なのは、「どこを苦手としているか」が見えたこと。
それが分かった時点で、もう次のステップに進んでいる。
今回は、実際の試験に近い内容を意識して作成していますが、
図や記号の問題までは再現しきれなかった点はごめんなさい。
時間のあるときに、またチャレンジしてみてください。
繰り返すうちに、きっと感覚がつかめてくるはずです。
____
この記事の内容は、現場で長く溶接に関わってきた経験をベースにまとめてるよ。
「この人どんなキャリアなんだろ?」と気になったら、プロフィールで少しだけ覗いてみてね。








